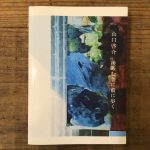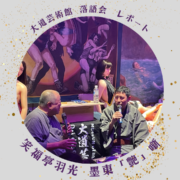千葉市美術館のミュージアムショップ BATICAの本棚作りを担当している本屋しゃん。せっかく、千葉にゆかりができたこともあり、千葉の展覧会情報をお届けしたいと思います。千葉には、千葉市美術館だけではなく、ステキな美術館や博物館がたくさんありますよ〜!
本日、ご紹介したいのは、千葉県佐倉市に位置する「国立歴史民俗博物館」で開催中の特集展示(国際展示)「東アジアを駆け抜けた身体―スポーツの近代―」です。
わたしの趣味は日々のジョギング。もともと運動音痴で、体育の授業は嫌いでしたし、どちらかというとスポーツを避けてきた人生でした。しかし、ある日、所謂、ダイエットをしよう! という気持ちで、近所の公園を走ってみました。外を走るのは緊張したなあ。はじめは1km走っただけで息切れ、しかし、走り終わった後の気持ちよさに味をしめ、次の日も、また次の日も走るようになったら、今ではすっかり好きなことのひとつになりました。あんなに苦手意識があって、どちらかというと嫌いだったスポーツが趣味に昇華されたのは自分ではびっくりな変化です。
「スポーツ」という概念が、外国から日本にやってきたのは1900年代。なんだかつい最近のことなんだな、としみじみ。いや、しかし、まてよ、わたしが苦手だったスポーツを克服するより、「はじめてスポーツに触れた人々」はきっともっと大変な思いをしたのではなかろうか? もしかしたら、はじめから、めっちゃたのしー!とすんなり受け入れていたのかしら? そんな疑問が湧いてきます。なんでも、はじめの一歩を踏み出すってすごいことですよね。「東アジアを駆け抜けた身体―スポーツの近代―」は、国立台湾歴史博物館と国立成功大学との共同研究成果発表として、身体の改変や近代オリンピックへの参加という歴史的経験を共有してきた日本と台湾における「近代化」の過程を見つめ直し、スポーツの近代史を紐解く展覧会。その中で、日本にスポーツの概念が入ってきてからの約150年間の歴史を、日本植民地期の台湾人アスリート、張星賢(ちょう せいけん 〜1989)の生きた道のりを中心に据えて振り返っています。

張星賢さんのスタートのお姿!なんて美しいのでしょう。スタートの一瞬を切り取った写真から、颯爽と駆け抜ける張さんの走りと、風をきる感覚、大地をふみならす、砂埃……人の動きの体とともに、それを取り巻く環境の動きが伝わってくるかのようです。
張さんは、日本植民地期の台湾人アスリート。1910年10月、台湾中部の中心都市・台中に生まれ、台中商業学校在学中に、陸上競技の素質をメキメキと発揮!そして早稲田大学専門部に進学し、競走部に入部。(なるほど、当時は陸上部ではなくて、競走部と呼んでいたのかあ)。早々に実力を認められ、翌年のロサンゼルスオリンピックに日本選手として出場する切符を手にし、卒業後は、南満洲鉄道株式会社に就職、1936年のベルリンオリンピックの日本代表にもなられたそうです。わあ!まさに、日本、台湾、満州国、アメリカ、ヨーロッパ……世界中をその足で駆け抜けられたのですね。
 早稲田大学大学史資料センター蔵.jpg)
ん〜、みんないい笑顔!こんな笑顔を見ていると、走ることを愛して、充実した日々だったんだろうなと想像できますよね。しかし、張は、日本人による台湾人差別など、アスリートとしての人生を保証してくれる植民地の体系と、現実との矛盾の間で葛藤を強いられていたようです。一人のアスリートの人生に焦点を当てることで、見えてくる歴史。誰かが拾わなければ、こぼれ落ちてしまっていた視点かもしれません。きっと、本展は単なる資料展示にとどまらず、一人に焦点を当てるからこそ見えてくる、生々しく息遣いが聞こえてくる歴史が刻まれているのだと感じます。
張さんのスタートの美しいお姿を見た後に、この絵を見て見ましょう!美しいというより、おもしろくて楽しい光景に映りますねえ。幕末から明治初期にかけては、まだスポーツという概念がなかった日本。これは、その頃にスポーツを曲芸の一種のようなものとして「ウンドヲ」として認識されていたことがわかる図です。スポーツとはなんぞや、こんな感じか? と、新たな概念に触れた人の想像力が吹き出しているわけですね。今、こうしてみると、滑稽さすら感じてしまうけれど「はじめまして」を吸収して、咀嚼して、理解することは大変なことですよね。

1860年代 国立歴史民俗博物館蔵
なんでも、近世までは、膝を曲げた状態の「なんば歩き」や前かがみ、猫背の姿勢は普通のこと。だけど、幕末から近代において、このような姿勢が西洋人から奇異なものというまなざしを向けられるようになり……日本人は、まず膝や背を曲げず直立する姿勢や靴を履いて歩行することを必要とされたとのこと。新しい眼差し、新しい概念の流入とともに、身体も変えていかなくてはいけなかったわけですね! わたしはすぐに猫背になってしまうことが悩みなのですが、近世では、そっちの方がむしろ普通だったのか。「普通」が時代によっていかに流動していくか、では「普通」ってどこにあるんだということも、考えさせられますね。
他にも、本展は、近代の学校運動会に関連する錦絵、写真、肉筆漫画など約120点の資料を通し、さまざまな資料を通じて、スポーツの近代史を紐解きます。錦絵や写真、肉筆漫画などの展示があるとなると、アートファンにも楽しい展示ですね。


そして、忘れてはならないのが、今回の展示が国立台湾歴史博物館と国立成功大学との共同研究成果発表であること。残念ながら、新型コロナウイルス感染症の感染予防・拡散防止に伴う休館措置のため開催中止となってしまいましたが、「昆布とミヨク-潮香るくらしの日韓比較文化誌」展など、国立歴史民俗博物館では、国境を超えての共同研究の成果を展覧会を通じて発信し続けてくれています。まさに、同館は、一方的な視点ではなく、国境を超えて、双方の視点から「民俗」を理解することができる場所です。
コロナ禍の中、海を越えての旅はおろか、外出がままならない今ですが、そんな中だからこそ、世界中の人つながる工夫を多くの人たちが試みている今、同じ時代に、同じ地球に生き、同じ苦難をともにしている人々の歴史や生活を知ることができる国立歴史民俗博物館の展示は大切な気づきをもたらしてくれるのではないでしょうか。
「東アジアを駆け抜けた身体―スポーツの近代―」展は、2020年の開催予定でしたが、感染拡大にともない、オリンピック・パラリンピックと開催延期され、2021年の開催となりました。本展を通じて、張星賢が駆け抜けた時代に触れることで、スポーツをはじめとし、未曾有の現代を力強く生きるヒントを得ることができるかもしれません。
よ〜し!明日、ジョギングをするときは、張さんのことをちょっと思い浮かべてみようかな。そしたら少しでも美しい姿で走れるかしら。
展覧会情報
特集展示(国際展示)
「東アジアを駆け抜けた身体(からだ) ―スポーツの近代―」
開催期間:2021年1月26日(火)~3月14日(日)
(3月~:9時30分~17時00分(入館は16時30分まで))
会場:国立歴史民俗博物館 企画展示室B
(〒285-8502 千葉県佐倉市城内町 117)
料金:一般:600円 / 大学生:250円
※詳細は、公式WEBページをご覧ください。
https://www.rekihaku.ac.jp/exhibitions/special/index.html#special

-3-180x180.png)